お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2019.03.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
17日の日曜日は、目黒で行われた三旗塾オープン講座に参加してきました!!
この講座、当初の会場側のキャパは60名だったらしいですが、なんと参加者130名、ギュウギュウに詰めて、実にいい感じの熱気でした☆
(キャンセル待ちもずいぶん出たようです。)
やっぱ講演会場はすし詰めがいいね☆
この日の演者さんは、テレビ等のメディアで大活躍されている鍼灸師の若林理砂先生と、(一社)北辰会代表、藤本新風先生でした。
若林先生の取り組みは、非常に分かりやすく、人柄的にもストレートであり、しかもそれをご自身が楽しんでやっておられるなあ、という印象を受けました。
今後、ご自身の治療院を、数人の武術の指導者と組んで、薬店とトレーニングスペースを併設した治療院にするらしく、こういったやり方も、
今後の一つの在り方だろうと思います。
また、SNSなど、ネットを駆使して、体調不良を抱えている人などの「特定の条件の」人とどんどん繋がれる時代、若林先生のおやりになっているような、
「東洋医学的な健康相談を目的としたオンラインサロン」
や、
「メディアを駆使した情報発信」
をなさる鍼灸師の先生は、今後どんどん増えそうな予感を感じました。
(ただ若林先生も仰っていたように、そうそう簡単ではないと思いますが。。。)
オンラインサロン上の患者さんは極端な虚証が多いというのも、個人的には興味深いと思いましたね。
そして後半は新風先生による講義と実技。
多少の機材トラブルや準備不足なんかはありましたが、いつも通り、マズマズうまくいったと思います。
アンケートが楽しみですね。
終わった後は三旗塾の先生方と呑み。。。
最終的にはヒドイことになりました。(苦笑)
そして今日は東京衛生学園の謝恩会です。
昨日会ったメンバーと、また会います☆(^^)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.17

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
イヤーしかし、老いも若きも男も女も、皆さん花粉症ですな。。。
インフルエンザの後は花粉症、次はなんだ、梅雨が来るから、うつ病か!?(~_~;)
今や国民の5人に一人が花粉症と言われ、国民病と言われますが、僕が子供の頃は、花粉症の人なんてほとんど見かけませんでしたね。
単純に花粉の飛散だけでなく、大気汚染や水質汚染、食品添加物や社会構造などなど、様々な問題が複合的に関与して、この現状になっているのでしょう。
僕自身は幼少の頃から、アレルギーは全くないと思っていましたが、今から約20年ほど前、東京に来てから、年によっては少し出るようになりました。(T_T)
しかし、抗アレルギー剤や、抗ヒスタミン薬、ステロイドなどの西洋医学的治療は、これまでまったく、マジで一回も使ったことがないです。
(苦笑・・・まあ、幸いにも不要で済んだ、というところですな)
あれらの対症療法としての効果は素晴らしいようで、患者さんを診ていると、ほとんどの方が何かしら飲んでおられますね。
ですので、鍼灸臨床サイドでは標本同治、あるいは本治のみ、という感じで処置をすることが多いですね。
最近では西洋医学的な根治療法と言われる「減感作療法」も、皮下注射じゃなくて錠剤や液体でやるんだとか。
・・・さて、今後はどうなるやら、って感じですね。
僕は何年か前に、咳が数カ月止まらなくなった時に、自分で鍼をしても漢方飲んでも、先輩にかかってもダメだった時があり、仕方なく初めて呼吸器内科にかかりまして、
その時に呼吸器の検査のついでにアレルギー検査をしたら、スギやヒノキに陽性が出ていました。
毎年、鍼と漢方でいよいよどうにもならなくなったら、西洋医学的対症療法にお世話になろうかな、と思っているのですが、今のところコントロール出来ています。(゚∀゚)
今度、ちょっと機会をいただいて花粉症に関して人前で喋るので、最新情報も踏まえて勉強し直そうと思います。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.08

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここまでのお話し
小建中湯について 2 参照
別にシリーズ化する気もなかったんだけど、書き始めたら何となく、
「あれも書いとこ、これも書いとこ。」
ってなって、徐々に続いてしまった、この「脾胃モノ有名漢方薬」シリーズ。(笑)
特に脈絡もなく、患者さんを診ていて、よく使われているものを書いています。
(こんなん書いてたら、キリがないね。。。)
もちろんながら、漢方薬というのは、鍼灸と同じように、芯となる流儀や考え方に基づいて、論理的整合性、一貫性をもって処方されるべきもので、
決して症状のみ、病名のみから場当たり的に処方されるものではないと理解しています。
だから僕は、全くの素人さんが、エキス剤とはいえ、ドラッグストアで簡単に漢方薬を購入できる現状、ネット通販で自分の症状から調べて入手しては、
サプリメント感覚で次から次に試しまくる現状にも、正直反対です。
もちろん、自分で鍼や温灸を買って適当に試すことにも、厳しいようですが反対です。
僕は鍼灸臨床家であり、畑は違いますが、今後も優れた漢方家の先生方と協調しながら、真面目に東洋医学をやっていきたいですね。(^^)
前置きが長くなりましたが、今日は「補中益気湯」です。
(これで一応いったん締めとしましょう。)
実は2013年の記事に、チラッと登場しました。
この方剤の出典はあの中国金元の4大医家の一人、李東垣(1180-1251)先生の『脾胃論』であり、『中医臨床のための方剤学』によれば、構成生薬は
人参9g、白朮9g、黄耆15~30g、当帰9g、柴胡3g、陳皮6g、炙甘草6g、升麻3g
となっています。
効能は補中益氣、昇陽挙陥、甘温除大熱であり、主治は気虚下陥、気虚発熱とあります。
まあ要は、”黄耆”という生薬を主薬とし、結果的には中焦の気(脾気)を補って、気を昇らせ、脱肛や子宮脱などの”中気下陥”の症状を改善させ、
場合によっては気虚発熱を改善するという目論見の薬です。
李東垣は『内外傷弁惑論(1247)』の中で、発熱には外邪が入って邪正闘争の結果発熱するものと、脾胃が弱ったことにって発熱するものがあり、
脾胃が弱った場合については甘温剤で脾胃をフォローすることによって清熱することが出来ると主張しました。
ここで重要なのは、熱証モノは脾胃を補えばいい、という理解ではもちろんなく、その熱証症状、所見が、”何によるものなのか”を鑑別診断できる物差しを身に付けることですね。
この物差しになるのが脈診、腹診をはじめとした”多面的観察”であります!!
患者さんが、
「先生風邪ひいたー。。熱が出たー。。。」
と、言っていたからといって、それがどういう病因病機によるものなのかに対する理解ですね。
意外と臨床上、脾胃を補うことによって熱証症状が取れていくことはあります。
アトピー性皮膚炎なんかでも、たまに経験しますね。
実際に漢方家の先生の中には、補中益気湯を使ってアトピーに効果を挙げておられる先生も少なからずおられるようです。
刮目すべき理論です。
〇
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.05

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここまでのお話し
小建中湯について 参照
前回、小建中湯の話がエラク中途半端に終わったので、続きを書きます。(^^;)
小建中湯は、実は以前このブログにもチョコッとだけ登場しています。
小建中湯は、桂枝湯のアレンジ版であることは前回お話ししました。
しかし、ここら辺を細かく話していくと、『傷寒論』の太陽病の講義みたいになってしまうので、ここではしません。(^^;)
(興味ある人は、無数に出ている『傷寒論〇〇』という本を5冊くらい買って勉強しましょう。)
小建中湯は、今日では東洋学術出版の『中医臨床のための方剤学』で「脾虚肝乗」という言い方をするように、脾の臓が弱ってしまって、肝の臓とのバランスが崩れたものによく使われます。
もちろん、この薬のもともとの出典は『傷寒論』ですから、寒邪に傷られた傷寒病の、ある段階においても使いますし、これをやって治らなかった場合に小柴胡湯を使う、という流れもあります。
「小柴胡湯」を含む記事 参照
また、『傷寒論』の中の小建中湯適応の脈診所見に「陽脈濇、陰脈弦」という、解釈次第では色々拡大出来るような脈状の表現も出てきます。(*‘∀‘)
あるいは『金匱要略』の中にも、この薬は”虚労病”、”黄疸病”、”婦人病”のところに出てきます。
さらに『金匱要略』では、目的に応じて、小建中湯に黄耆(おうぎ)を加えて「黄蓍建中湯」という薬を提示していたり、少し時代が下って中国唐代、
孫思邈(そんしばく 581?-682)の『千金翼方』では小建中湯に当帰(とうき)を加えた「当帰建中湯」があったり、日本の江戸期、あの華岡青洲(1760-1835)の
『瘍科方筌(ようかほうせん)』では、この「黄蓍建中湯」と「当帰建中湯」を組み合わせて、さらに膠飴を使わずに「帰耆建中湯(きぎけんちゅうとう)」という方剤を創方し、
癌が潰れて膿が止まらず、日々憔悴していくほどの重篤な病人に使用していたようです。
華岡青洲という人物 参照
・・・まあしかしこの、
「肝と脾のバランスが崩れている」
ことが、カゼから花粉症からアトピー、リウマチ、癌まで、あらゆる現代病の根本原因になっていることは、臨床上、実に多いと思います。
ここんとこをシンプルに調整してくれる薬だからこそ、約2000年の風雪に耐えて来れたんでしょうね。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.04

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここまで、中焦(脾胃)の異常に対してよく処方されている漢方薬を、いくつか紹介してきました。
大建中湯について 参照
前回、大建中湯を紹介したので、なんか小建中湯を紹介しないのは気持ちが悪い。。。
・・・ということで、ついでなんで小建中湯を紹介します。(゚∀゚)
(処方されている患者さんも結構いるしね。)
小建中湯も、大建中湯と同じ「温裏剤」のグループです。
出典はもちろんあの『傷寒論』ですから、約2000年の風雪に耐えてきた名方と言えます。
この処方は非常に有名です。
漢方薬の王様の一人と言っていい、「桂枝湯」という薬がありますが、この桂枝湯の中の「芍薬(白芍)」という生薬を倍の量にしたのを「桂枝加芍薬湯」といい、
それに「膠飴(こうい:みずあめ)」を加えたのが「小建中湯」です。
『中医臨床のための方剤学』によれば、効能は温中補虚、和裏緩急、主治は中焦虚寒、脾虚肝乗とあります。
・・・おっと、ここまで書いたら時間切れ。
続きは次回。(笑)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.03

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここまで、四君子湯を処方されていた患者さんがたまたま見えたことをきっかけに、脾胃が病んだ時の処方についてツラツラと書いてみた。
もちろん、湯液の専門家の先生から見たら笑っちゃうような、超大づかみの内容であり、間違いや曲解もあるかもしれないが、そもそもこのブログを専門家向けに書いたことは、この10年間、ほぼない。
あくまでも、この医学を全く知らない人、あるいは懐疑的な人(つまりほとんどの日本人(苦笑))を中心に、専門的な内容といっても、せいぜい初学者やディレッタントに向けて、
この医学の特長、特性を少しでも知ってもらおうと、書いている。
一応自分なりに調べた上で書いているつもりですが、もし間違い等があったら、すぐに修正しますので、ぜひご教示いただきたい。
・・・まあともかく、昨日、「安中散」と方意が似ている方剤として、「大建中湯」に触れた。
この方剤、意外と現代の消化器外科のドクターが処方することが多いようだ。
なぜなら、大腸癌術後の腸閉塞(イレウス)に有効であるという論文が出ているからだそうだ。
論文等については、大建中湯のツムラさんの説明書に簡潔に紹介されている。
このように、東洋医学的な整体観、人体観、疾病観に則った、弁証論治の結果としてではなく、西洋医学的な病名に基づいて、論文で有効性が一定認められているから、
という理由で、漢方薬が乱用されているケースが少なくないようだ。
実際にこれを処方している医師に、『金匱要略』や、その後の名医が残した「大建中湯」に関する諸文献を読んだ上で使用している先生は少ないのではないだろうか。。。
全く東洋医学の教育を受けたことがない医師が、腹診も脈診も舌診もせず、東洋医学的な人体観(臓腑経絡学説や病因論等々)や、弁証問診もしない中で、
西洋医学的病名のみを頼りに同一の漢方薬を長期に乱用する。。。
・・・これはー、どうだろうか。
やはり、この考え方は、生薬資源の無駄遣いに、繋がらないだろうか。
私の知己の、漢方家は、みな口を揃えてそう言っている。。。
脾胃の病といっても、ここまで紹介したパターンもそうだし、まだまだ他にも、たくさんある。
それを的確に分析し、良化や悪化の流れを考えて、その時点で最もフィットする方剤や、鍼灸で言えば配穴や手技を選び、経過に応じて加減していくことが出来るのが、東洋医学の叡智だと思うんですが。。。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.02
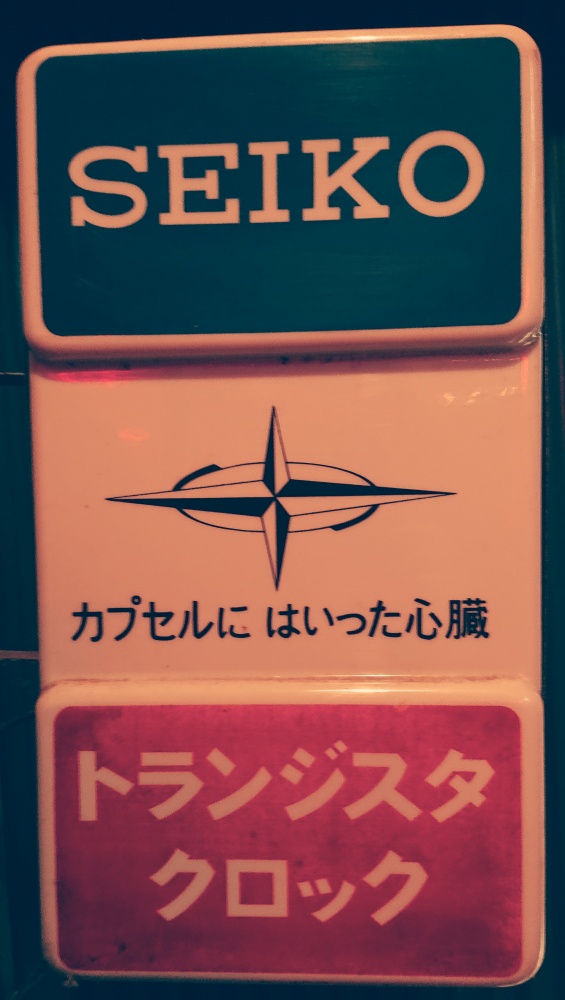
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
ここんとこ、
という記事を書きました。
ついでなんで、中焦(脾胃)モノを、もうちょっと書いときましょう。
単純に脾胃の病と言っても、寒熱虚実、他臓腑との関わり、色々あるんです。
それをきちんと分析して、きちんとした処置をしていかなかったら、治るもんも治りません。
今日は「安中散」です。
こないだ、これを処方されている胃痛、パニック障害の患者さんが見えました。
マズマズ効いていたようです。
これも出典は中国宋代、『和剤局方』であります。
『中医臨床のための方剤学』によると、
組成は肉桂(桂枝)4g、延胡索3g、牡蛎3g、小茴香1g、甘草1g、縮砂(砂仁)2g、高良姜1g、
効能は温中降気、止痛、
主治は裏寒の疼痛、
と、あります。
これは「温裏剤」のグループであり、『金匱要略』に出てくる、有名な「大建中湯」の附方(方意が類似している薬)として紹介されています。
要するに中焦を温めて寒邪を散らし、冷え痛みをとるのが方意な訳ですが、方意が似ているのに、組成はまったく違います。(苦笑)
ここが漢方の面白いところなんでしょうね。
・・・まあ、鍼灸もそうですね。
同じ効果を狙って、全然違う経穴に、全然違う鍼灸をすることは、日常的にあります。
「大建中湯」の場合は、脾胃+主に肺腎を意識しながら、急いで冷えと上逆を取りにいく方剤であるのに対して、「安中散」は脾胃+主に肝を意識して、
長期的な冷えに対して、”理気”というアプローチをかけていますね。
鍼灸でも、大建中湯的な効果を狙うのと、安中散的な効果を狙うのとでは、配穴から手技から違います。
・・・ところで「大建中湯」は、消化器外科でエラク使われるようです。
これにも触れときましょうか。
(キリがねえなー(;’∀’))
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.03.01

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
昨日、四君子湯と六君子湯という記事を書きました。
ついでなんで、比較的有名にして、「六君子湯」と似ているところのある「平胃散」についても書いておこうと思います。
・・・まあ、僕は鍼灸の臨床家でありますので、これらの薬の、より臨床的な解説は、漢方家の先生のサイトにお任せするとして、これらの方剤の使い分けの際に考えるような内容が、
我々の臨床においても、微妙に配穴や補瀉やその評価に関わってくるんだよ、という話でも書いておこうと思います。
「平胃散」の出典も、「四君子湯」と同じく、宋代の国定処方集である『和剤局方』であります。
この『和剤局方』は、以前紹介した森道伯先生の臨床にも出てくる、大変重要な処方集ですね。
『中医臨床のための方剤学』によれば、平胃散は「袪湿剤」のグループであり、処方構成は蒼朮15g、厚朴9g、陳皮9g、甘草4gとあり(生姜、大棗を含める場合もあり)、
効能は燥湿運脾、行気和胃、主治は湿困脾胃とあります。
四君子湯や六君子湯と違って、人参、白朮、茯苓ではなく、蒼朮を多めにドーンと入れてあることで、「燥湿(湿邪を乾かす)」の効果を主に狙っている訳ですね。
つまり、湿邪の邪気実によって、脾胃の働きが抑えられているものに対する処方な訳です。
脾・胃 参照
四君子湯、六君子湯の”補法(補気)”をベースとした世界とは違う、”瀉法(袪湿)”の世界ですね。
中国清代の傳山(1607~1684)の『傳青主女科』では、この処方に朴硝(含水硫酸ナトリウム)を加えて、死胎の娩出に使っているというから、興味深い。
清明院もここ最近、二十四節気では「雨水」に入り、「啓蟄」の前であり、月齢では新月に向かい、こないだの雨で気温がガクンと下がり・・・、
という流れの中で、まさに「平胃散証」、という患者さんがチラホラ見えました。
これは鍼でやるなら、足三里や豊隆を瀉法か?あるいは太白を瀉法か??
それとも脾兪や胃兪か?
あるいはお灸でやるか??
どれが一番、平胃散チックか??
こう考えながらやるってのも、楽しいもんだねー(゚∀゚)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.28
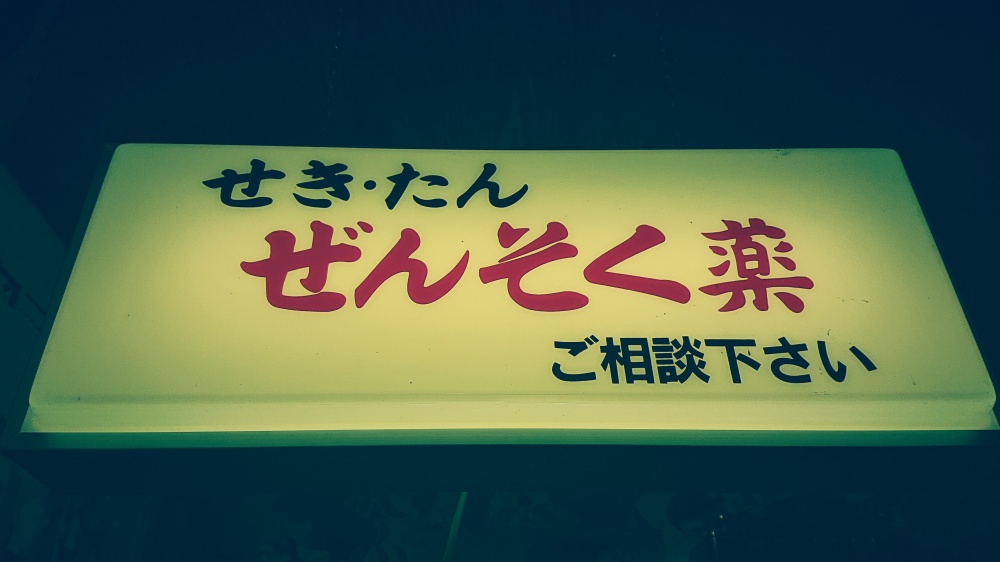
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ、患者さんで、「四君子湯」という漢方薬を処方されている方がいらっしゃった。
・・・そこでふと、昔のことを思い出した。
ずいぶん前のことだが(15年以上前かな?)、蓮風先生が実技デモで腹診をしながら、
「これは四君子湯の証や!四君子湯と六君子湯は違うぞ!!どう違うか、お前分かるか!?」
と、当時の講師の先生が指されて、その先生が答えられずにアワアワしていたのを思い出した。
そのあと確か、太白に鍼をなさっていたように思う。
・・・で、当時、帰ってから、四君子湯と六君子湯の違いについて一生懸命調べたことがあった。
久々に思い出したんで、ここに書いておく。
〇
四君子湯の出典は中国宋代の国定処方集である『和剤局方(1110)』で、この方剤は『中医臨床のための方剤学』では「補気剤」のグループの薬だ。
(「補気剤」の代表選手、といってもいい方剤みたいです。)
内容は人参6g、白朮9g、茯苓9g、炙甘草6gとのこと。
(本によって別説もあるようだが。。)
効能は益気健脾、主治は脾気虚とある。
人参と炙甘草で津液を補い、白朮、茯苓では湿邪を取る、この相反する作用をもって、全体としては脾の臓の弱りをフォローする薬、というワケだ。
(相反する作用を持つ生薬をあえて配合して、結果的に効果を高める、これを相反相成というそうです。)
それに対して、六君子湯はどうか。
出典は明代の虞摶(ぐたん 1468-1517)による『医学正伝(1515)』だそうで、四君子湯よりもずいぶん後になって考案された処方らしいですが、
これも分類的には「補気剤」のグループで、四君子湯の脾気虚がさらに進んで、脾胃ともに気虚(脾胃気虚)を起こし、さらに湿痰を生じているものに対する方剤で、
前述の四君子湯の4味に加えて、和胃降逆の作用を持つ小半夏湯の内容(半夏・生姜)を加え、さらに理気健脾、燥湿化痰の陳皮と、補脾、養営の大棗を加え、
全部で8味もの、やや複雑な構成になっている。
総じて効能は補気健脾、和胃降逆、理気化痰、主治は脾胃気虚と痰湿、ということになる。
清代の名医で有名な程国彭(ていこくほう 1662-1735)の『医学心悟(1732)』に、
「・・・気虚挟痰、清陽不昇、濁陰不降、即上重下軽、六君子湯主之。・・・」
と、簡潔に述べているように、臨床的には脾胃の弱りによって中焦から上昇(特に上焦)に痰湿が停滞しているものに使うとある。
四君子湯も六君子湯も、どちらも脾気虚を補うという点では同じだが、六君子湯の場合は胃の気虚と痰湿の邪実が射程に入っている、ということですね。
鍼では、四君子湯の場合は大白への補法でいいと思うが、六君子湯の場合は、大白だけで終われるのは相当腕達者だと思う。
二穴に分けるか、腹を使うか・・・。
いずれにせよ、所見も評価も、全然異なる。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.21

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ、患者さんで、
「生理痛にノニジュースが良いと聞いて、飲むようにしたら痛み止めを使わないでもいられるようになった!」
という人がいらした。
この手の話は、臨床をやっているとゴマンと出会うが、バカにしてはならないと思っています。
(藤本鉄風先生の教えですね。)
・・・今回も、ほう、と思って、少し調べた。
清明院から歩いてすぐのところに、巨大なビルが建っている「ノニ」。
こないだ話題になった「青汁王子」じゃないけど、こういった健康食品産業ってのは、スゴイもんだね。(゜o゜)
新宿にビルが建つなんて、鍼灸院ではとても無理っす☆
10代の頃から、朝から晩まで勉強して、臨床して、休みの日は勉強会行って、やっとこさっとこ学術を身に付けて、それでもやっとこさっとこメシが食えているくらいなのに、
とある健康食品を開発して、上手に宣伝して、通販で全国に売ったら、新宿に巨大なビルが建つ。。。
これが社会の現実です。(;’∀’)
・・・まあいいっす、僕は僕で、大都会新宿の片隅で、コツコツとやります。(`・ω・´)ゞ
さてこの「ノニ」ですが、東南アジアからオーストラリアにかけての太平洋熱帯地域全域に生育する常緑低木または小木だそうです。
日本では沖縄に「ヤエヤマアオキ」という和名の自生種があるそうで、古くから果実や根や茎が薬用に使われてきた歴史があるそうです。
まあ、「ノニ」の効果については、色んなサイトで、色んなこと(効果効能)が実に景気よく書かれています。(苦笑)
・・・でもまあ、こちらのサイト様に書かれているように、科学的根拠は不十分、という、いつものやつではないでしょうか。
ただ、冒頭にも述べたように、「科学的根拠が不十分」だから大したものではない、と即断するのは違う。
因みにノニは、morinda属の植物なんだそうだが、同じmorinda属の植物を使う生薬に「巴戟天(はげきてん)」という生薬があります。
毓麟丸(いくりんがん)、巴戟丸(はげきがん)、金剛丸(こんごうがん)といった、聞きなれない処方に使われるようで、中薬学では「補益薬」のグループで、特に「助陽薬」に分類されます。
(まあ、陽気を補うグループです。)
巴戟天は根っこの部分を使うらしいが、腎陽虚+寒湿邪の女子胞の冷えからくる不妊症や生理痛、生理不順などによく使う生薬だそうで、
ノニもこれと似たような効果が期待できるとすれば、生理痛が取れたというのも納得できる。
しかし、熱帯地域にある植物で、冷えを取るとは。
清熱にいきそうなイメージを持っていましたが、陰虚熱、湿熱には禁忌だそうです。。。
意外とこういう、患者さんのいう、健康食品で奇効が得られたという話が、鍼灸治療や、養生研究の役に立つことがある。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.10.15
2025年9月の活動記録2025.10.10
清明院16周年!!!2025.10.01
2025年 10月の診療日時2025.09.20
2025年8月の活動記録2025.09.01
2025年 9月の診療日時2025.08.15
2025年7月の活動記録2025.08.01
2025年 8月の診療日時2025.07.04
2025年6月の活動記録2025.07.01
2025年 7月の診療日時2025.06.26
2025年5月の活動記録2025.06.01
2025年 6月の診療日時2025.05.10
2025年4月の活動記録2025.05.01
2025年 5月の診療日時2025.04.04
2025年3月の活動記録2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02
2024年3月の活動記録2024.04.01
2024年 4月の診療日時2024.03.14
2024年2月の活動記録2024.03.01
2024年 3月の診療日時2024.02.15
2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04
3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03
3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!