お電話
03-6300-0763
10:00~21:00(完全予約制)
2019.04.29

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
◆そーいや、あいつがいたわ。
2018年の夏のある日、つけ麺を食いに行く途中、ふと、かつての部下である友岡清秀の顔が脳裏に浮かびました。
彼は、今から10数年前、私が開業する前に副院長を務めていた鍼灸院時代の部下であり、鍼灸師でありながら、退職後は大学院に進学し、医学博士の学位を取った秀才です。
彼が順天堂大学医学部に、現在助教として勤務しているのを知っていましたので、
「あそうだ、順天堂はどうだろうか。」
と、何となく思いつき、電話を一本。
こういう時の、私の電話の内容は極めてシンプルです。
「・・・こういう訳なんだけど、学生さんで東洋医学やりたい子いないかな?」
「あー、たぶんいると思います。。。」
「じゃあ聞いといてー」
これで決まりました。(笑)
その後、食事会かなんかで学生にこの話をし、学生さんの何人かが乗り気で、人数集めてくれて、とりあえず講義を開催できる体裁が整ったのが、去年の年末、というワケです。
また、友岡君を通じて、彼が学位論文でお世話になった指導教授である、谷川先生と私に、数年前から面識があったことも大きかったです。
話しが実にスムーズに進みましたね。
こうした、思い付きからの御縁で、記念すべき第一回目が実現した訳です。
・・・とはいえ、その伏線は10年以上前からあったことが分かりますね。
彼も、清明院元副院長の松木宣嘉と同じく、私が『医道の日本』に書いた、私塾的な勉強会メンバーの一人でした。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.28

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************
![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
◆まずはリサーチ
2017年に日本中医学会で成田先生の御活動を知り、何とか関東で同じようなことを出来ないかと考えるとともに、まずは現状を把握してみよう、と思いました。
ちょうど中医学会に行く前に、千葉大の和漢診療科を見学させていただいたことがあったので、千葉大の先生方に聞いてみたり、東京に帰って来てから、
今度は北里大学の東洋医学総合研究所に研修に伺ってみたり、日本東洋医学会の地方会に参加してみたり。。。
・・・そうして、大体の現状を把握しました。
分かったのは、
1.鍼灸と漢方をバランスよく教えているところは少ない
(ほとんどは漢方偏重であり、鍼灸は体験させるのみという感じで、体系的に鍼灸医学を教えているとは言えない)
2.東洋医学教育は大学間でバラつきがあり、ほとんど教えてない、というところが多い
(全国共通のカリキュラムもない、医師国試にも出ない、教えられる講師が足りない)
3.学生には意外と東洋医学を学びたいというニーズはあるが、受け皿がない(少ない)
4.大学をまたぐような学生のネットワークも少ない
というあたりです。
(もし間違っていたらご指摘ください。)
これは大いに改善の余地があるなあ、と思い、何か出来る筈だよなー、と悶々と考えていたのが去年の春~夏くらい。
そして、夏のある日、つけ麺でも食いに行くかな、と思って運転していた車の中で、ふと閃きました☆
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.20

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
これまでのお話し
「五行」のはたらき 2 参照
◆稼穡とは
まず、土の働きである「稼穡(かしょく)」というのは、学生さんにとっても覚えにくい、現代ではなかなか使わない言葉なんですが、
「稼」=穀物を植える
「穡」=穀物を穫り入れる
という意味であり、まさに農業そのもの、といった意味です。
古代中国は、もちろんながら農耕民族、農耕文化であり、
「土≒農業する場」
であったわけです。
日本でも、平安時代の仏教説話集である『地蔵菩薩霊験記』に、
「稼穡は皆万民の命を重くするところ天下の重宝なり」
と出てくるそうですし、
「土≒農業する場」
という理解、設定には、何ら違和感はなかったでしょうね。
(『精選版 日本国語大辞典』参照)
因みに、魏の宋均の注である、『春秋』の緯書(※)である『春秋元明苞』では「土=吐」と説明し、後漢の許慎の『説文解字』では「生きてるものを吐き出す」と説明し、
「土」という文字に含まれる「二」は大地の表面と地中を示し、「|」は生命が地中から地表に芽を出している姿、と説明しています。
(※)・・・漢代、儒家の経書を神秘主義的に解釈した書物。
まあつまり、大地(土)は、気をたっぷりと蓄えており、様々なものを生み出す場だよ、と。
故に「土は万物の母」であると言われたりもします。
(因みに『老子』の第一章に「万物の母」という言い方が出てきますが、これは五行の土の働きを言ったものではなく、天地そのもの(宇宙)のことを言っています。)
「老子」という人物 参照
老子第一章の「万物の母」と五行の土の「万物の母」を絡ませた説明では、この論文が面白かったですね。
土は万物の母であり、方位(空間)では中央に位置し、季節(時間)では各季節の終わりと始まり(土用)、あるいは日本では梅雨と秋雨の時期(※)を指します。
((※)・・・『内経気象学入門』P37~参照。『黄帝内経』の諸篇では”長夏”といって6月に土があてられていますが、これは日本の気候とは必ずしも一致しません。)
つまり自然界の中で、中心であり、キーであり、緩衝材であり、バランサーであり・・・、行き過ぎない状態をもって良しとします。
人間の生命で言えばまさに「胃の気」ですね。
東洋医学的に細かく言えば、臓腑経絡では脾の臓(足太陰脾経)と胃の腑(足陽明胃経)であり、経穴では陰経の兪原穴、陽経の合穴が配当されます。
脾・胃 参照
五行の土(どろ)が配当されている臓腑経絡、経穴に鍼灸をする時、一つには
「土気を動かしている」
という意識を持って、効果を観察するといいと思います。
たとえばよく使う「天井穴」とかね。(゚∀゚)
続く。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.04.17

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
今日は2019.4.17でございます!!
今日から5.5までが「春の土用」であります。
現在、二十四節気では「清明」節です。
(清明院の清明です。(^^))
「清明」の意味は「清浄明潔」であります!!
二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯では、今は末侯の「虹始見(にじはじめてあらわる)」であります。
虹が始めてあらわるということは、梅雨に向かって空気が潤ってくることを示します。
・・・で、次の節は「穀雨」であります。
そして、土用が明けて、「穀雨」の次の節、5.6からがいよいよ「立夏」であります。
また、今年の穀雨~立夏は新元号である、「令和元年」でもあります。
春の終わりに潤った空気が、患者さんに何を起こすか、また、改元によって忙しくなる患者さんに、何が起こるか、GWの連休の過ごし方はどうするのか、
これらの諸問題をよくよく考えて、慎重に対処しないといけません。
土用で穀雨だから、空気が潤うから、イコール脾が弱るだの、イコール土克水で腎に来るだの、そういう短絡的発想はやめましょうね☆
やはり多面的観察が大事。
でも、時節も大事。
我々は、生物学的人間であると同時に、社会学的、文化的人間を診ているのであります。
蓮風先生や、『内経気象学』の橋本浩一先生も良く仰るが、東洋医学では、基本として運気や時節を鑑みつつも、常に実際の気候気象、風向や気温湿度、
その患者に起こった現象等々から、多面的観察の上で総合判断しなさいよ、という、重要な教えです。
陰陽論を、機械的に運用するという愚を犯してはならない。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.28
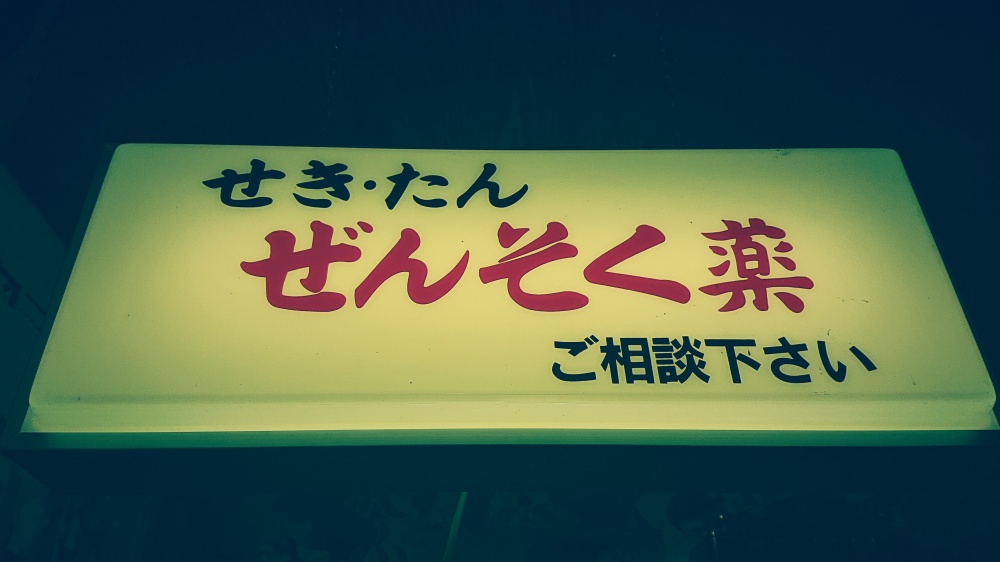
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
こないだ、患者さんで、「四君子湯」という漢方薬を処方されている方がいらっしゃった。
・・・そこでふと、昔のことを思い出した。
ずいぶん前のことだが(15年以上前かな?)、蓮風先生が実技デモで腹診をしながら、
「これは四君子湯の証や!四君子湯と六君子湯は違うぞ!!どう違うか、お前分かるか!?」
と、当時の講師の先生が指されて、その先生が答えられずにアワアワしていたのを思い出した。
そのあと確か、太白に鍼をなさっていたように思う。
・・・で、当時、帰ってから、四君子湯と六君子湯の違いについて一生懸命調べたことがあった。
久々に思い出したんで、ここに書いておく。
〇
四君子湯の出典は中国宋代の国定処方集である『和剤局方(1110)』で、この方剤は『中医臨床のための方剤学』では「補気剤」のグループの薬だ。
(「補気剤」の代表選手、といってもいい方剤みたいです。)
内容は人参6g、白朮9g、茯苓9g、炙甘草6gとのこと。
(本によって別説もあるようだが。。)
効能は益気健脾、主治は脾気虚とある。
人参と炙甘草で津液を補い、白朮、茯苓では湿邪を取る、この相反する作用をもって、全体としては脾の臓の弱りをフォローする薬、というワケだ。
(相反する作用を持つ生薬をあえて配合して、結果的に効果を高める、これを相反相成というそうです。)
それに対して、六君子湯はどうか。
出典は明代の虞摶(ぐたん 1468-1517)による『医学正伝(1515)』だそうで、四君子湯よりもずいぶん後になって考案された処方らしいですが、
これも分類的には「補気剤」のグループで、四君子湯の脾気虚がさらに進んで、脾胃ともに気虚(脾胃気虚)を起こし、さらに湿痰を生じているものに対する方剤で、
前述の四君子湯の4味に加えて、和胃降逆の作用を持つ小半夏湯の内容(半夏・生姜)を加え、さらに理気健脾、燥湿化痰の陳皮と、補脾、養営の大棗を加え、
全部で8味もの、やや複雑な構成になっている。
総じて効能は補気健脾、和胃降逆、理気化痰、主治は脾胃気虚と痰湿、ということになる。
清代の名医で有名な程国彭(ていこくほう 1662-1735)の『医学心悟(1732)』に、
「・・・気虚挟痰、清陽不昇、濁陰不降、即上重下軽、六君子湯主之。・・・」
と、簡潔に述べているように、臨床的には脾胃の弱りによって中焦から上昇(特に上焦)に痰湿が停滞しているものに使うとある。
四君子湯も六君子湯も、どちらも脾気虚を補うという点では同じだが、六君子湯の場合は胃の気虚と痰湿の邪実が射程に入っている、ということですね。
鍼では、四君子湯の場合は大白への補法でいいと思うが、六君子湯の場合は、大白だけで終われるのは相当腕達者だと思う。
二穴に分けるか、腹を使うか・・・。
いずれにせよ、所見も評価も、全然異なる。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.02.17

**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
北辰会カルテに、「発汗の左右差」を問う問診項目がある。
発汗に左右差を感じたことの無い人からしたら、
「そんな現象、あんの??」
と思うだろうが、これ、意外といらっしゃいます。
特に腋窩。
緊張すると、どちらかの腋窩にばっかりに汗が出る、という患者さんは、結構いる。
これは中医学では「汗出偏沮(かんしゅつへんそ)」といいます。
これにも色々な考え方(弁証分型)があるのだが、明末清初の名医、張璐(1617-1700)の『張氏医通』によれば、
・・・夏に半身に汗出るは、気血満たず、内に寒飲。
偏枯(片麻痺)、夭(夭疽、あるいは早死に?)の兆しなり。
大剤の十全大補湯、人参養栄湯、大建中湯に行経豁痰薬を加味して治す。云々・・・
この証は血虚に属すが、四物湯などの陰薬を使わないのは、経絡の閉滞を招くからである。
〇
ちょっとした左右差であっても、要注意。
また、ある種の左右差ものに、迂闊な滋陰、補血は危ない。
補気+行経豁痰という考え方、マジ重要。
一穴でやるなら、どこでやる??
【参考文献】
『症状による中医診断と治療 上巻』燎原書店
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.01.19

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
二十四節気、明日で「大寒」ですね。
過去記事を読むと、2011年から、この時期になると春を感じ、何かしら書いていることが多いね。(笑)
大寒になったということは、立春の前であり、こないだも書いたが、「冬の土用」に入っていることを大いに意識するべきです。
(特に東洋医学の臨床家は。)
秋冬の陰から春夏の陽へ、陰陽が大きく変動する時です。
当然、それの影響を人体は受けますので、人それぞれに変化を感じます。
場合によっては崩れます。
その崩れ方の一つが、インフルエンザの大流行だったりするわけです。
インフル狂騒曲 参照
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2019.01.16

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
毎日寒いですな。
毎年恒例で、インフルが暴れていますが、慌てず騒がず、粛々と鍼と養生で調えましょう。(^^♪
まずは防寒、防乾、そして鍼灸で心身を調え、あとはまあ、マスク、手洗い、うがいです。
(・・・俺はマスクしてねえけど、患者さんから咳を浴びせかけられることがあるので、しようかな。。(苦笑))
二十四節気では小寒から大寒に移ろうとしていますが、明日が土用の入りです。
2019年の冬の土用は1.17~2.3です。
土用とは四立(立春、立夏、立秋、立冬)の手前18日間のことで、四季それぞれの最後の18日間のことです。
夏の土用の丑の日にウナギを食べるのが有名ですが、四季それぞれに土用はあります。
今は立春の手前であり、「冬の土用」となります。
体感温度は寒いですが、患者さんの体を診ていると、僕的には微妙に春の気配を感じますね。
外感病であっても、それを考慮すると治りがいいようですな。(゚∀゚)
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.12.20

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
本日は診療を早めに終わらせて、とある場所で講義へ。。。
夜しか来れない患者さん達、大変申し訳ありません。<m(__)m>
これですね、まだオープンには出来ませんが、今年の夏あたりから考え、可能性を模索していたことがついに実現しました。
日本伝統鍼灸学会、北辰会年末代表講演と、今年の大イベントはすでに消化しましたが、何気に今日のこれが、来年の私の活動を占う上では、
裏の大一番かもしれません。(笑)
あまり盛り上がらなければ、この一回で終了もあり得ます。(苦笑)
盛り上がれば、もしかすると、大きな動きになるかもしれません。
ひょっとすると、歴史的な一歩になるかもしれない。
・・・それは、鍼の神のみぞ知るところです。
ま、一先ず、気合い入れていきます☆
うまくいったら、来年あたり、このブログで大いに語ることが出来るかもしません。
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2018.10.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、
募集内容の詳細はこちら!!
**********************************************************************************************![]()
![]()
↑↑↑ ↑↑↑
こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>
クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!
**********************************************************************************************
前回のお話し
ローズマリーティー?? 参照
◆そもそもどこに生えてたの??
植物とその効能を考えていく時、まずは
どこに自生していた植物なのか(原産地)
を知ることで、ある程度そのものが持つ性質を把握できることがあります。
ローズマリーというのは、地中海沿岸地方が原産地なんだそうです。
(ふむふむ、ヨーロッパの植物な訳ですな。)
地中海沿岸地域ということは、「地中海性気候」といって、比較的温暖な気候で、冬には一定の降雨があるが、夏は日ざしが強く、乾燥するそうです。
植物としてはローズマリーの他に、夏の乾燥を利用した耐干性の樹木性作物(オリーブやブドウなど)、冬の降雨を利用した冬小麦栽培が行われるほか、
乾燥して牧草の育たない夏に、家畜を高山へ移動する移牧も行われるそうです。
これらを組み合わせた混合農業のことを「地中海式農業」といい、オレンジ、レモン、イチジク(無花果)、コルクガシ、月桂樹(ローレル、ローリエ)などが栽培され、
オリーブ油、ワインなどが多く出荷されているそうです。
(やはり、暖かい気候で、しかも乾湿の偏差が大きい地域であるせいか、東洋医学的には理気活血、清熱解毒モノがよく採れるようですね。)
・・・で、そんな環境にあって、ローズマリーはシソ科に属する常緑性低木で、和名では「マンネンロウ」と呼ばれ、中国では「迷迭香(めいてつこう)」と呼ばれます。
(この日中でのネーミングの由来が気になりますね。あとで触れましょう。)
生葉もしくは乾燥葉を香辛料、薬(ハーブ)として用い、花も可食であり、水蒸気蒸留法で抽出した精油も、薬として利用されるそうです。
ふむふむ、大活躍だね、ローズマリー。
続く
読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!
2012.07.08
2016.05.09
2016.04.12
2016.04.28
2015.06.04
2012.12.23
2014.02.17
2014.04.26
2025.10.29
2025年 11月の診療日時2025.10.15
2025年9月の活動記録2025.10.10
清明院16周年!!!2025.10.01
2025年 10月の診療日時2025.09.20
2025年8月の活動記録2025.09.01
2025年 9月の診療日時2025.08.15
2025年7月の活動記録2025.08.01
2025年 8月の診療日時2025.07.04
2025年6月の活動記録2025.07.01
2025年 7月の診療日時2025.06.26
2025年5月の活動記録2025.06.01
2025年 6月の診療日時2025.05.10
2025年4月の活動記録2025.05.01
2025年 5月の診療日時2025.04.04
2025年3月の活動記録2025.04.01
2025年 4月の診療日時2025.03.13
2025年2月の活動記録2025.03.01
2025年 3月の診療日時2025.02.06
2025年1月の活動記録2025.02.01
2025年 2月の診療日時2025.01.21
順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10
2024年12月の活動記録2025.01.02
2025年 1月の診療日時2025.01.01
謹賀鍼年!!2024.12.28
年内診療終了!!2024.12.14
2024年11月の活動記録2024.12.01
2024年 12月の診療日時2024.11.07
2024年10月の活動記録2024.11.01
2024年 11月の診療日時2024.10.10
清明院15周年!!!2024.10.09
2024年9月の活動記録2024.10.01
2024年 10月の診療日時2024.09.19
2024年8月の活動記録2024.09.01
2024年 9月の診療日時2024.08.03
2024年7月の活動記録2024.08.01
2024年 8月の診療日時2024.07.10
患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05
2024年6月の活動記録2024.07.01
2024年 7月の診療日時2024.06.05
2024年5月の活動記録2024.06.01
2024年 6月の診療日時2024.05.10
2024年4月の活動記録2024.05.01
2024年 5月の診療日時2024.04.13
(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02
2024年3月の活動記録2024.04.01
2024年 4月の診療日時2024.03.14
2024年2月の活動記録2024.03.01
2024年 3月の診療日時2024.02.15
2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04
3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!